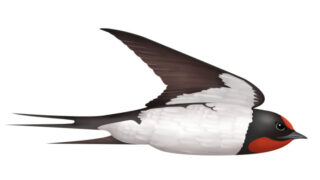春という言葉使われていて、春の天気示す言葉と思われがちなのですが、実際季節でいえば秋の終わりから冬の初めにかけての言葉なのです。これは小春という単語の意味を知れば簡単に理解できると思います。小春は旧暦10月の別名であり、これは今でいう11月から12月初旬の時期であり、日和は空模様などの意味があります。
小春日和は暖かい晴天という意味
小春日和は11月ごろの秋にある春みたいな温かな天気表現するとき使う四字熟語となります。
また、文化庁がした世論調査によれば約4割が春先の暖かな天気の意味だと思ってると発表されました。
小春日和とは
小春日和とは、春の初めによく見られる、穏やかで暖かい天気のことです。
小春とは「小さな春」という意味で、由来は中国の陰暦の10月に由来しています。
陰暦の10月は、現在で言うと11月から12月上旬に当たり、この時期は気候が穏やかで、春のような暖かさになるため、小春日和と呼ばれています。
小春日和は、春の始まりを告げる季節で、人々は小春日和の日に、お花見やピクニック、散歩などを楽しみます。また、小春日和は、農作物にとっても良い天気で、農家は小春日和の日に、種まきや田植えなどの農作業を行います。
小春日和は、人々にとって、心が安らぐ幸せな季節です。小春日和の日に、大切な人と過ごす時間を大切にしましょう。
小春日和の季節や天気
小春日和は、春の初めによく見られる天気ですが、秋にも見られることがあります。小春日和の季節は、気候が穏やかで、気温が10度から20度程度です。
天気は晴れや曇りで、風が弱いことが多いです。
小春日和の日は、空気が澄んでいて、星がきれいに見えることもあります。
小春日和の日は、人々が外出する絶好の機会です。
お花見やピクニック、散歩などを楽しむ人が多く、農家は種まきや田植えなどの農作業を行います。
小春日和の日は、心が安らぐ幸せな季節です。

高原と青空
小春日和は気象庁の正式な用語
小春日和は気象庁でも用いられる正式な用語であり、晩秋から初冬にかけての暖かな晴天と定義されています。
そして、これは意味に合った通り春ではなく秋の晴天を示す時に使えて、その定義は決まってないようですが、時期に関しては小春の期間に当たる11月のみ用いられてます。
小春日和は類義語がありますが、秋晴れで秋の晴れた日を示す点でとても似た意味があります。時期については小春日和は旧暦10月の時期のみ使えますが、秋晴れは文字通り秋全般に用いられて、より広い意味があるようです。
インディアンが使っていたもの
アメリカにも小春日和みたいに秋の暖かな日を示す言い回しがありますが、インディアンサマーは秋にとっては季節外れの暖かく穏やかな天気を示します。
その由来ですが、原住民のインディアン、ヨーロッパから来た人たちが土地をめぐりあらそった時代さかのぼって、劣勢のインディアンは土地取り戻すのに戦います。
その戦いの日、秋の晴れた日をよく選んでいて、これは霜により足元悪くなり逃げるのに都合がよかったからようです。よって小春日和という四字熟語は春という感じで使われていますが、秋の天気を示すために春と誤解が生じやすいようです。
手紙のあいさつ
身近な話題の天気、ビジネスで使って手紙のあいさつなど多くの場面で出てきますので、しっかりと意味を理解すれば自信をもって使えるようになると思います。
青天白日とは
青天白日の意味ですが、青天と白日に分け考えられます。
青天とは青の空であり、空が青いのは雲が見当たらなくて、よく晴れてるのです。
白日は白い太陽の光であり、太陽の光白く見えるのは日差し強い晴れた日なのです。
青天、白日はどちらも快晴を象徴する言葉であり、青天白日はよく晴れた空を意味します。
もう一つの意味はやましい気持ち、行動が一切ないというもので、空を心、雲を疑惑に例えれば雲ひとつない青のそらは澄み渡ったこころであるといえます。
大昔に登場した言葉

朝霧高原からの富士山
雲一つない、明るい空という意味で青天白日用いたものには、青天白日の元運動会が催されたという例文がありますが、聞かれたことはありませんか?運動会当時強く晴れた日であったことを意味します。
やましい気持ちがないという意味で用いた物では、わたしが家事を手伝うのはお小遣いもらいたいからでなく良心の負担抑えてあげたいと思うからで、私は青天白日だという例文です。
また疑いがはれ無罪になるといった意味の例は、冤罪証明され、彼はやっと青天白日のみになったという文があり、犯罪者と疑われてたものの結局その無罪明らかになったことを示します。
むかし中国が唐という国の次代があり、この時代中期に「かんゆ」という人が登場しました。彼の書いた書物に青天白日が登場します。
春の空は、様々な表情を見せてくれる
春の空は、一日のうちに様々な色に変化し、その変化は、私たちに春の訪れを感じさせ、心を癒してくれます。
春の空は、私たちに、自然の美しさと、生きることの喜びを感じさせてくれます。
春のことわざ
有名なことわざをいくつか掲載します。
春眠暁を覚えず
中国の唐代の詩人、孟浩然の詩「春暁」の一節です。「春の夜の眠りは、夜が明けたことも気づかないほど心地よく、なかなか目が覚めない」という意味です。
このことわざは、春の夜の穏やかで心地よい眠りをたとえて言ったものであり、また、春の訪れを喜ぶ気持ちの表れともいえます。
春の晩飯後三里(はるのばんめし あとさんり)
「春の晩飯後三里」のことわざは、「春は日が長いので、夕飯を食べた後でも三里(約12キロ)も歩けるほど」という意味です。
これは、春は日照時間が長く、気温も暖かいため、人々が活動的になる時期であることを表しています。また、春は新しい始まりの季節であるため、人々が新しいことに挑戦したり、冒険に出かけたりする時期でもあるのです。
このことわざは、春の明るい未来への希望を込めた言葉であると言えるでしょう。
春宵一刻値千金(しゅんしょういっこく あたいせんきん)
中国の詩文に由来することわざで、春の夜は趣が深く、そのひと時は千金にもかえがたい価値があるという意味です。
春は、自然が生き生きと動き出す季節です。空気は澄んでいて、花々が咲き、鳥たちがさえずります。そんな春の夜は、心が安らぎ、幸せな気持ちになります。
このことわざは、春の夜の美しさや、そのひと時の大切さを教えてくれる言葉です。私たちは、春の夜を大切に過ごし、その幸せを噛み締めていきたいものです。
台風一過とは
他に天気の四字熟語で思い出すのは台風一過という言葉があります。
一つ目は台風一過とは台風が通り過ぎ風雨が収まって晴れ渡り良い天気になることを意味します。
二つ目は台風一過後天気が良くなる意味が転じて、騒動のあと気持ち晴れ渡るという意味もあります。
騒動を台風に例え、そうどう終えた後の地ついた状況、心境を示す四字熟語となります。余談ですが、時々見る「台風一家」という表記と混同してしまい、これでは台風の家族という意味で、本来の意味からかけ離れてしまうようです。
まとめ
春の夜は、春の美しい景色を楽しみ、心を休めるのに最適な時間です。
このことわざは、私たちに春の夜の美しさや、そのひと時の大切さを教えてくれる言葉です。
私たちは、春の夜を大切に過ごし、その幸せを噛み締めていきたいものです。