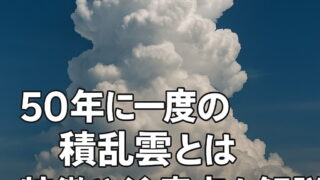天気予報は、私たちの生活に欠かせないものです。しかし、なぜ天気予報にはルールがあるのかご存知ですか?
この記事では、天気予報のルールとは何か、日本の天気予報のシステム、そしてその理由について解説します。
日本の天気予報のルールとは?その特徴とメリットを解説
天気予報とは、気象衛星からの映像などを参考にして、今後天気や気温、風向きなどがどのように変化するかを考えてみた結果から予想しているものです。
予報とは言いますが、正確には「予想」と考えた方がいいでしょう。
その為、当たらずとも遠からずといったことから、全く当たらなかったということもままあり、絶対性、確実性が必ずあるとは言えないものです。
天気予報のルールとは
天気予報は、気象庁や民間気象会社が、観測やシミュレーションに基づいて行うものです。
天気予報には、天気図や降水確率など、さまざまな要素が含まれます。
天気予報のルールとは、これらの要素をどのように組み合わせて天気予報を行うかという基準のことです。
日本の天気予報のシステム
日本の天気予報のシステムは、気象庁が中心となって運営しています。
気象庁は、全国に観測所を設置して気象データを収集し、それをもとに天気予報を行っています。また、気象庁は、コンピュータを使って天気のシミュレーションを行い、天気予報の精度を向上させています。
日本のシステム
日本では独自の気象衛星「ひまわり」からのデータと、全国に約1300箇所存在する自動地域気象観測システムの「アメダス」を利用して、各地の天気予報を気象庁から公式に発表しています。
このひまわりは日本だけでなく、アジア圏やオセアニアまで広くカバーしている衛星の為、他国にもそのデータを提供しています。
ある程度の技術とその為の予算まで考えることができる先進国でないと、衛星の打ち上げやその運用は難しい為、この気象衛星を打ち上げている国は世界でもそうはありません。
よって、日本のひまわりは、先のような諸国の天気予報に多いに貢献していると言うことができます。
となりの国のシステム
韓国では、2010年に独自の「千里眼」という名前の気象衛星を打ち上げており、現在ではそちらも自国の天気に関連する各種のデータの収集に活用しています。
独自の衛星を打ち上げている会社もある?
天気予報は先のような、気象庁が公式に発表したものだけではありません。
誰でも発表できるの?
日本ではこの天気予報に関して少しルールがあり、誰でも独自に予報していいというものではありません。自由に発表できるのは、気象庁の公開したものだけです。
逆に言うと、気象庁の公開であれば自由に発表できる為、ニュース番組で芸能人がお天気コーナーに出てきて、天気に関連する予報などを読み上げるといった場面が見られますが、その内容は気象庁の公開したものに限られています。
気象予報士とは
ただし、国家資格である気象予報士であれば、独自に予報を公開することが許可されています。
どのようなデータを参考に、どういった内容を公開しようが自由となっており、民間の気象予報会社にはそのような気象予報士が何人も在籍し、気象庁とは別に独自の予報を発表していることがあります。
気象庁の予報を参考にするものの、詳しく考えてみた結果、それとは少し違う予報とするといったことも多いです。
実際にテレビ番組でもチャンネルによって違う場合がありますね。
気象予報会社によって何故違う?
また、大きな気象予報会社になると、ひまわりとは別に独自の気象衛星を打ち上げています。
それだけ費用を掛けて天気予報をしているとなると、採算が心配になりますが、契約者のみに有料で天気予報を公開することで成り立っており、一般のものより詳細な天気予報が必要な特殊な企業がその顧客となっていることが多いです。
詳細な天気予報って?
前項で挙げた詳細な天気予報とは、日本であれば市町村の単位で15分ごとの天気に関連するあらゆる情報といったような内容になります。
もっと詳しいものになると、5分単位のようなこともあり、同じ市町村でも北部と南部にまで分かれて発表されることもあります。
天気予報は企業に大事
それだけ詳細なものが必要になるのは、天候がビジネスに直結する企業に他ならず、主に先物取引に関するビジネスを行っています。
この先物取引においては、天候の変化だけで使っている各種の取引商品の価格が上下することさえ珍しくないからです。
簡単な例では、雨が続きそうだと分かれば、その雨によって被害を受けそうな穀物の先物価格が上昇するという具合で、一般的な天気予報ではとてもそういったビジネスには足りません。
有料天気予報が必要?
そこで、有料でも詳細なピンポイントの天気予報を得ることで、それを役に立てているという訳です。
ネットのサイトで簡単に見ることができるような天気予報は、全て気象庁の発表したものだと考えて構いません。(誰でも自由に公開できるので、広く利用されています)
ひまわりのデータは、条件を満たせば誰でも利用が可能となっています。
ただし、天気予報として発表することは気象予報士でないとできない為、天気に関連することに興味のある人は、自分で考えてみた予報を公開することまで考えて、気象予報士の資格を目指してみるといいかも知れません。
天気予報のルールの理由
天気予報のルールは、天気予報の精度を向上させるために設けられています。
天気予報のルールは、天気予報の専門家によって、常に改良されています。
天気予報のルールは、私たちの生活にさまざまなメリットをもたらしています。
たとえば、天気予報は、農業や漁業、交通など、さまざまな産業に役立っています。
また、天気予報は、私たちの日常生活にも役立っています。
たとえば、天気予報は、私たちが服装や外出の計画を立てるのに役立ちます。
まとめ
天気予報のルールは、私たちの生活に欠かせないものとなっています。天気予報のルールについて理解することで、より正確な天気予報を利用することができます。