日本には数々のことわざが存在し、「急がば回れ」「犬も歩けば棒に当たる」など誰もが知っているであろうものの他に、天気に関することわざも数多くあります。
ことわざには天気の予測に役立つものもあり、知っておくと便利です。
風は、私たちの生活に欠かせない自然現象です。
しかし、風がどのようにして吹くのか、その仕組みを理解している人は少ないのではないでしょうか。
ここでは、天気の雨や風に関することわざとその意味を紹介します。
雨がつくことわざ一覧はこちらでも紹介しています。↓↓
知っているようで知らない?天気にまつわる名言ことわざと雨がつく諺一覧
2023.6.2風がつく諺を追加しました。
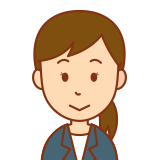
天気と風と雨に関することわざシリーズの紹介です。
今回もイトポン先輩と真面目に一生懸命にお届けします。
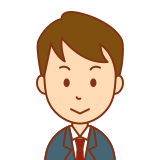
キナポン、アドバイザーよろしくお願いします。
コホン、では、天気に関するもことわざの多くは先人の知恵が詰まったものと言われてます。
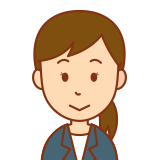
天気に関することわざの多くは天気予報がなっかた昔の時代に天気を読む先人の教えが入っているんですよ。
では、最初のことわざ紹介です。
(先輩緊張してるみたい・・。フフフ)
天気や雨・風に関することわざと風がつくことわざ一覧
雷が鳴ると梅雨が明ける
日本には約1ヶ月半ほどの梅雨があり、長い間雨が降り続けます。これはオホーツク海高気圧と太平洋高気圧がぶつかることで梅雨前線ができ、梅雨前線が日本列島付近に停滞するからです。
梅雨明けが近づいてくると梅雨前線が北上、太平洋側から湿った暖かい空気が流れ込んできます。この空気が山の斜面を昇って上昇気流となり、積乱雲が発生。
高い場所ほど空気は冷たくなるため、湿った空気が冷やされて氷の粒となり、次第に大きくなった氷の粒が重さに耐えきれず地上に落ちてきます。落ちてくる氷の粒同士がぶつかり合うと静電気が起きて、雲の中に電気がたまっていきます。たまった電気が地上に向かって落ちてくるのが雷です。
つまり、 梅雨前線の北上により雷が発生する、梅雨前線が北上すると梅雨明けが近い。「雷が鳴ると梅雨明け」ということわざは、自然をよく観察していることわざといえるでしょう。
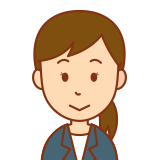
雷は大嫌いですが、梅雨が明け、夏本番がくるぞっ!と言ってるような、雷が季節を知らせてくれる合図みたいですね。
朝焼けはその日の洪水
朝焼けがみられる日には、やがて大雨になるという意味です。
朝焼けとは、日の出のころに東の空が赤く見えることです。
朝には太陽の高度が低く、地上までの距離が長くなります。太陽の光には、青、緑、赤、紫などさまざまな波長の光が含まれていて、それぞれ波長の長さが違います。波長の短い青い光は散乱をして人間の目には見えなくなってしまいますが、波長の長い赤い光だけが届いて赤く見えるのです。これが朝焼けの仕組みです。
鮮やかな赤は空気中に水蒸気が多いためみられる現象です。水蒸気が多いと雲が発生をして、雨が降る可能性があります。
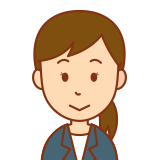
虹のレインボーは人間の目で見えるのが七色だからって聞いたことがあります。本当はもっとたくさんの色があるそうなんですよ。虹もよく考えると不思議なんですが、朝焼けも水蒸気が関係してるんですね。
では、次のことわざです。
朝虹は雨 夕虹は晴れ

朝虹
朝焼けはその日の洪水と似た意味のことわざに「朝虹は雨 夕虹は晴れ」ということわざがあります。
プリズムを通した光を見たことがありますか? プリズムに光を通すと、光の屈折が起こって赤、黄色、青、緑、紫などさまざまな色の光を見ることができます。
虹もプリズムと同じような現象です。太陽の光が空気中の水滴によって屈折・反射されることで虹が見えるようになります。
朝に虹が見えるときは西側に雲がある状態です。この雲が東側に移動してくると雨が降る可能性があります。
逆に夕方に虹が見えると翌日は晴れる可能性が高くなります。夕方に虹が見えるときは東側に雲があり、西側はよく晴れている状態のため、翌日は晴れるのです。
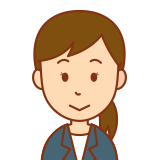
虹の見え方でこの後の天気を予測するってロマンチックですね。
昔の人は太陽の位置関係と虹で天気予測していたんですね。
春北風に冬南いつも東は常降りの雨

春北風
風が関わることわざもあります。
このことわざは、春には北風、冬には南風、また四季を通して東風はいつも雨という意味です。
東からの湿った空気が流れこんでくると、雲が発生して雨が降る可能性があります。
春の北風や冬の南風による雨は地形の影響を受けます。風が吹く山の斜面側では湿った空気が上昇して雲が発生し雨を降らせますが、反対側の斜面では雨を降らせた後の乾いた空気が流れこんできてよく晴れます。
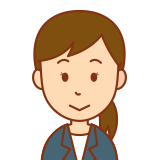
もしかして、三国志の諸葛亮孔明は赤壁の戦いで風が変わることを知ってたと言われますが、このことも知ってたのでしょうね。
大昔からの言い伝えがあるなんてロマンを感じます。
明日には明日の風が吹く
明日は今日と違った風が吹きます。昨日は北風が強かったけれど、翌日になったらピタッと風が治まっていた、そんな経験はありませんか?
明日のことをくよくよ思い悩んでいてもどうにもできません。天気のことを人間の力でどうにもできないのと同じです。悩んでいても仕方がなく、明日には別の流れに変わる可能性があるので、くよくよせずにいましょうといった意味です。
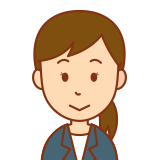
「明日は明日の風が吹く」って決め台詞カッコイイですね。くよくよしたってしょうがない。明日は来るんだからって、ね イトポン先輩!
あれ?イトポン先輩間もなく終わりますよ!
雨ばかりだったり、暑い日が続いていたりすると気分が落ち込んでしまいがちですが、明日の天気はどうなるかわかりません。天気のことでくよくよせずに、明るい気持ちを持っていると毎日が過ごしやすくなるかもしれません。
嵐の前の静けさ
良く聞くことわざですね。
何かが起こりそうな予感の時に使います。
また不気味な平穏さの時にもったりします。
これは暴風雨が来る前に一時的に風雨が収まり静かな状態を表してます。
例えば台風の目に入った時にさっきまでの台風の風がピタっと止んだ経験などはありませんか?そしてまた吹き返しの強い風がやってきます。
そうした現象で嵐の前の静けさは日常的にもよく使われることわざですね。
雨垂れ石を穿つ
雨垂れ石を穿つ(あまだれいしをうがつ)の意味は根気よく努力を重ねていけば達成できるという例えになります。
雨垂れのようなポツンポツンと小さな雫でも長い年月をかければ石を砕いたり穴が空いたりします。
コツコツと努力すればいつか努力が実るとの意味で使うことわざです。
雨後の筍
雨後の筍(うごのたけのこ)は後から似たようなものが次から次へと出てくることわざです。
と言うのも雨が降った後は筍が次から次へと出てくる様子を現しています。
筍は成長も早いですよね。
例えば近くにマンション建設ラッシュが続くとあそこの一帯はまるで「雨後の筍のようにマンションが建っている」というように使ったりします。
風前の灯火
風前の灯火(ふうぜんのともしび)は灯火が風で消えそうな様子を現しています。
例えば戦国時代に例えれば危機が迫って今にも滅びそうな状況の時に「相手は風前の灯火だ。間もなく城も落ちるだろう」というように使います。
逆に「我が陣は風前の灯火だったが援軍が来たおかげでこの危機を脱する事が出来た」等の使い方もあります。
いずれも何かあれば直ぐにでも滅びてしまう状態の時に使うことわざと覚えておけば良いでしょう。
雨降って地固まる
よく聞くことわざですね。でも意味はと言うとなかなか説明できにくいことわざですね。
もめ事等があった場合に「その後はかえって良い結果をもたらす」意味になります。
もめ事は避けたいですよね。
しかしそのもめ事があったことにより、より良い方向に向かった時に使ったりします。
例えば幕末の明治維新に例えると対立していた長州と薩摩。
坂本龍馬の働きにより薩長同盟が成立。討幕に動き出す。
これこそ「雨降って地固まる」のことわざにピッタリと言ってはいいのではないでしょうか。
風前の灯火(ふうぜんのともしび)
風がつくことわざで有名なことわざです・
人の命のはかなさを例えたことわざです。
また、危険にさらされて今にも滅びてしまいそうな様子のときにも使います。
説は風が吹き付けるところに灯火があって、風で今にも火が消えてしまいそうに揺れている灯火を現しています。
良い意味では、困難や危険な状況にあってもひとかどの勇気や希望を持ち続けることを表現しています。
似たことわざで「風の前の塵(ちり)」というのもありますが意味は同じですが風前の灯火が有名ですね。
大風が吹けば桶屋(おけや)が喜ぶ
あることが原因となって意外なところに影響を及ぼし思いがけない結果を招く意味のことわざです。
なぜ桶屋?と思うかも知れませんが連想ゲームみたいになっています。
大風が吹く→砂ぼこりが目に入る→目を病んで目の不自由な人が増える→目の不自由な人の多くは三味線を引く→三味線に使う猫の皮が必要→多くの猫が捉えられる→猫が少なくんネズミが増える→ネズミは桶をかじる→桶が売れて桶屋が儲かって繁盛する。
というような説になっています。説からは江戸時代当たりを想像してしまいますね。
風林火山(ふうりんかざん)
「風、森、火、山」を意味します。
このことわざは、状況や困難な状況での勇敢さと戦略の重要性を表現しています。
風上に置けない
「風上に置けない」はことわざと名言の両方の要素を持っている表現と言えます。
意味としては「優れた人間や問題は、他の人や問題よりも上位の位置にいることが先にある」ということを示しています。
いると、風が向かうために、臭いや塵が遠くに飛ぶというイメージです。
そのため、風上に置かれることは好ましくありません。
「風上に置けない」は、特に仕事や競争の分野でよく引用されます。
競争社会においては、他の人や物事と比較されて優れた存在であり続けることが求められます。、他の人に追いつけないように自分を成長させる必要があるという意味が込められています。
波風が絶えない
意味は、「物事が常に変化し、動揺している状態」です。
このことわざは、政治や経済などの社会情勢が常に変化し、不安定な状態にあることを表すためによく使われます。
また、人間関係や仕事などの日常生活においても、常に変化や困難が起こり、波風が絶えない状態にあることを表すために使われます。
柳に風
意味は、「相手に逆らわず、なびくように、物事をうまく受け流す」です。
このことわざは、物事がうまくいかない時や、困難な状況に直面した時に、あきらめずに、うまく対処するという意味合いで使われます。
風雲急を告げる
意味は、「大事件が起こりそうな情勢が急速に悪化している」です。
このことわざは、政治や経済などの社会情勢が急速に悪化している状態を表すためによく使われます。
また、人間関係や仕事などの日常生活においても、問題が発生したり、状況が悪化したりしている状態を表すために使われます。
馬耳東風
意味は、「他人の意見や批評に注意を払わず、聞き流すこと」です。
このことわざは、中国の詩人・李白の詩「答王十二寒夜独有懐」に由来しています。
この詩の中で、李白は、他人の意見や批評に注意を払わず、聞き流す人のことを「馬耳東風」と表現しています。
順風満帆
意味は、「物事がすべて順調に進むこと」です。
このことわざは、船が追い風を受けて、帆をいっぱいに張り、軽快に進む様子から生まれました。
物事が順調に進んでいる時や、これから物事が順調に進むであろう時などに使われます。
月に叢雲、花に風
意味は、「好事には、とかく差し障りが多いことのたとえ」です。
このことわざは、月には雲がむらがっているように、好事には、とかく障害や妨害が入り、長続きしないことを表しています。
また、花に風が吹いて散ってしまうように、好事もすぐに終わってしまうことを表しています。
物言えば唇寒し秋の風
ことわざでも使われていますが「物言えば唇寒し秋の風」は、松尾芭蕉の俳句です。
意味は、「余計なことを言えば、そのためにかえって災いを招くということ」です。
この俳句は、秋の冷たい風に唇が冷たくなる様子から、余計なことを言えば、後悔することになるという戒めを表現しています。
馬の耳に風
意味は、「他人の意見や批評に注意を払わず、聞き流すこと」です。
このことわざは、中国の詩人・李白の詩「答王十二寒夜独有懐」に由来しています。
この詩の中で、李白は、他人の意見や批評に注意を払わず、聞き流す人のことを「馬の耳に風」と表現しています。
疾風迅雷
「疾風迅雷」はことわざではなく、四字熟語です。
意味は、「風のように速く、雷のように激しいこと」です。
この四字熟語は、自然現象から生まれた言葉で、物事が非常に速く、激しく変化する様子を表すために使われます。
五風十雨
「五風十雨」はことわざです。
意味は「気候が順調なことのたとえ。また、世の中が平穏無事であることのたとえ。」です。
五日ごとに風が吹き、十日ごとに雨が降るという意で、農作にちょうど適した気候であることから。
豆知識・風にまつわる仕組みや正体
風にまつわることわざは、風の力や変化を表現したものが多いです。
風は、私たちの生活にさまざまな影響を与えています。
風が吹けば、空気が入れ替わり、気温が変化します。
また、風は、雲を動かし、雨や雪を降らせます。風は、私たちの生活に欠かせない自然現象です。
風の吹く仕組みとは?
風は、気圧差によって吹くものです。
気圧とは、空気の重さのことです。
気圧が高い場所から気圧が低い場所へ、空気が移動することで風が吹きます。
気圧差とは?
気圧差とは、ある場所と別の場所の気圧の差です。
気圧差が大きければ大きいほど、風が強く吹きます。
コリオリ力とは?
コリオリ力とは、地球の自転によって生じる力です。
コリオリ力の影響で、風は北半球では右に曲がり、南半球では左に曲がって吹きます。
風の種類
風には、さまざまな種類があります。代表的な風には、次のようなものがあります。
- 貿易風
- 偏西風
- モンスーン
- 季節風
- 地形風
風の力
風は、さまざまな力を持っています。風の力は、次のようなものがあります。
- 風力
- 風速
- 風向
- 風量
風の影響
風は、私たちの生活にさまざまな影響を与えています。
風の影響には、次のようなものがあります。
- 気候
- 海流
- 農業
- 交通
- エネルギー
風の力を利用した発電
風は、私たちの生活に欠かせない自然現象です。
風が吹くと、気温が変化したり、雲が動いたり、海が波立ったりします。
また、風は風力発電や風車などの動力源としても利用されています。
風の正体とは?
風の正体は、空気の動きです。空気は、太陽の熱によって温められ、上昇します。
上昇した空気は、周りの空気によって押し下げられ、下降します。
この上昇と下降を繰り返す空気の動きが、風です。
風の強さは、気圧の差によって決まります。
気圧が高い場所から気圧が低い場所へ、空気が移動する際に風が吹きます。
風の強さは、風速で表されます。風速は、秒速で表され、1秒間に移動する距離を表します。
風の種類と特徴
風の種類は、大きく分けて3つあります。
- 地表風:地面の温度差によって吹く風です。
- 海風:海と陸の温度差によって吹く風です。
- 季節風:季節によって吹く風です。
地表風は、日中は地面が太陽に照らされて温まり、夜は地面が冷え込みます。
地面の温度差によって、空気の密度が変化し、風が吹きます。
海風は、海が陸よりも早く温まり、陸が海よりも早く冷えます。
海と陸の温度差によって、空気の密度が変化し、風が吹きます。
季節風は、季節によって、風向きや風速が変わる風です。
日本では、夏は南から吹く南風、冬は北から吹く北風が吹きます。
風は、私たちの生活に欠かせない自然現象です。風は、気温を変化させたり、雲を動かしたりして、私たちの生活に影響を与えています。また、風は風力発電や風車などの動力源としても利用されています。
まとめ
風は、私たちの生活に欠かせない自然現象です。風の吹く仕組みを理解することで、風の影響をより深く理解することができます。
雨と風にまつわることわざはいかがだったでしょうか。今後も天気にまつわることわざや四字熟語をテーマにした記事を作成していきますので当サイトにお寄りくださいませ。。
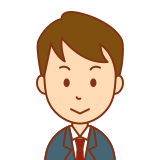
(スマホをイジイジしてる)
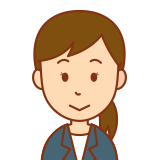
あっ なんか静かだと思ったらスマホでゲームしてる~!
せんぱーい!(ーー;)
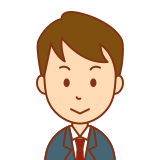
いや、あの、その、
次のテーマを探していました(>_<)。
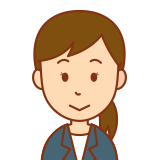
スマホ画面、見えたんだから~
焼肉おごってもらうからね!
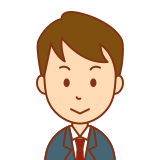
はいスミマセン(-ω-)/
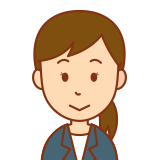
みなさん、いかがでしたか。今回はキナポンが一人でお届けしました!
また寄ってくださいね。





