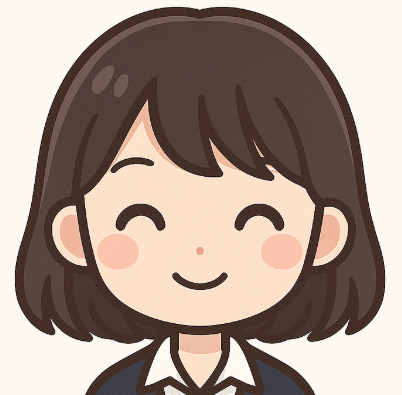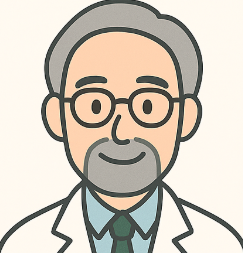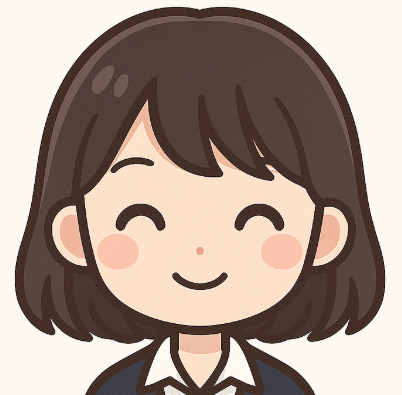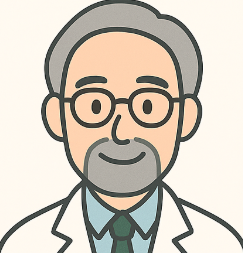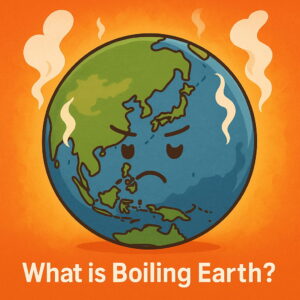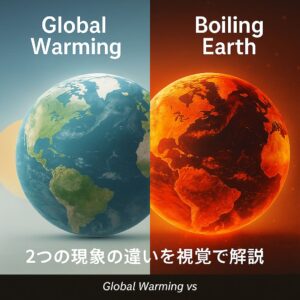最近、「地球沸騰化」という言葉をニュースやSNSで耳にする機会が増えました。
地球沸騰化とは、これまでの「地球温暖化」をさらに超えた異常な気温上昇を指す言葉で、今や世界中で深刻なテーマとなっています。では、なぜ急にこの言葉が注目されるようになったのでしょうか。
背景には、地球沸騰化の原因として、人間の活動による温室効果ガスの増加やエルニーニョ現象の影響など、複数の要因が重なっていることがあります。さらに、「2030年に氷河期が来るのか?」「2025年はなぜ暑すぎるのか?」「地球は今氷河期なの?」といった疑問も多く検索され、地球の未来に不安を抱く人が増えています。
この記事では、地球沸騰化と氷河期の関係をわかりやすく解説しながら、「地球沸騰化とは何か」「なぜこの現象が起きているのか」「どのような影響が身近に出始めているのか」などをやさしく説明します。
また、「地球沸騰化を止めるには?」という多くの人が抱く疑問にも触れ、私たちが今できることを考えるきっかけを提供します。
いま地球で起きている“異常な暑さ”の裏にある真実を、専門用語を使わずに丁寧に読み解いていきましょう。
◎この記事のポイント
・地球沸騰化とは何か、地球温暖化との違いがわかる
・地球沸騰化の主な原因(自然的・人為的要因)が理解できる
・地球沸騰化と氷河期の関係性や噂の真偽を知ることができる
・地球沸騰化を抑えるために今できる具体的な対策がわかる
地球沸騰化とは今なぜ注目されているのか
ここでは、近年よく耳にするようになった「地球沸騰化」という言葉についてわかりやすく説明します。
「地球温暖化」は以前から知られていますが、最近ではそれを超えるスピードで地球が“沸騰するように”気温が上昇していると警鐘を鳴らす専門家も増えています。
この章では、地球沸騰化の意味や背景、なぜ今この言葉が注目されているのかをやさしく解説していきます。
地球沸騰化とは簡単にどういう意味?
地球温暖化と地球沸騰化の違いとは?
地球沸騰化はいつから始まったのか?
地球沸騰化が注目されるようになった背景
地球沸騰化の影響が身近に現れている例
なぜ2025年は暑すぎると言われているのか?
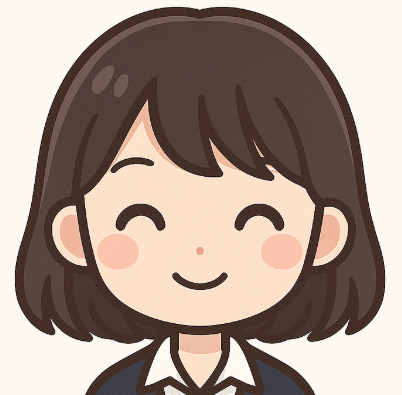
大学生みのり
「最近よく“地球沸騰化”って言葉を聞くんですけど、温暖化とどう違うんでしょうか?なんだか名前がちょっと怖いです…」
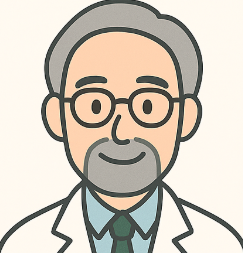
ドクター・モリ
「いい質問ですね。たしかに“沸騰”なんて聞くと、かなり深刻なイメージを受けますよね。実はこの言葉、最近の気温上昇の深刻さを象徴するために使われ始めたんです。これからわかりやすく説明しますよ」
地球沸騰化とは簡単にどういう意味?
地球沸騰化とは、これまでの「地球温暖化」という枠を超えて、気温の上昇がさらに加速し、まるで地球が“沸騰している”かのような状態に近づいているという状況を指します。
その言葉が注目されるようになったきっかけは、2023年に国連のアントニオ・グテーレス事務総長が「地球温暖化の時代は終わり、地球沸騰化の時代が来た」と発言したことです。この発言は、多くのメディアで取り上げられ、世界中で話題になりました。
なぜ「沸騰化」と表現するのでしょうか?
それは、単なる温暖化では説明できないほどの異常気象や高温が頻発しているからです。たとえば、これまで40度を超えることがなかった地域で、連日猛暑日が続くといった現象が実際に起きています。
以下の表に、「地球温暖化」と「地球沸騰化」のイメージの違いを簡単にまとめました。
| 用語 |
意味の違い |
| 地球温暖化 |
徐々に気温が上昇していく現象 |
| 地球沸騰化 |
急激かつ深刻に気温が上昇し、影響も広がっている現象 |
つまり、「地球沸騰化」とは気候変動がより深刻化しつつあることを警告するための言葉だと理解するとよいでしょう。未来の話ではなく、すでに始まっている現実なのです。
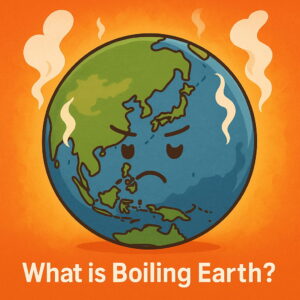
地球が沸騰している様子を表したイラスト
地球温暖化と地球沸騰化の違いとは?
この2つの言葉は似ているようで、危機感のレベルに明確な違いがあります。
まず「地球温暖化」は、産業革命以降、温室効果ガスの排出が増えたことによって地球全体の平均気温が徐々に上がってきた現象を指します。これまでの気候変動に関する議論や政策の中心にあるのがこの温暖化でした。
一方「地球沸騰化」は、温暖化がさらに悪化し、急激な気温上昇や災害がすでに“起きている”という危機的な状況を表現した言葉です。これは将来の予測ではなく、今まさに目の前にある問題を強調するために使われています。
具体的な違いを以下に整理してみましょう。
| 比較項目 |
地球温暖化 |
地球沸騰化 |
| 時期 |
徐々に進行 |
現在進行中で急速に進行 |
| 主な影響 |
気温の上昇、氷の融解、海面上昇など |
熱波、干ばつ、洪水、異常気象の頻発など |
| 危機レベル |
将来的な問題としての認識 |
現在の生活を脅かすレベルの問題 |
| 使用される場面 |
科学的な報告や研究 |
メディアや国際機関の強い警告 |
このように、「地球沸騰化」は“もう待ったなし”の状態を伝える言葉として使われています。地球温暖化は長年語られてきた問題ですが、地球沸騰化は、より緊迫感を持って対策が求められるフェーズに入ったことを示しています。
この違いを知ることで、より現実的な視点から地球環境について考えるきっかけになるでしょう。
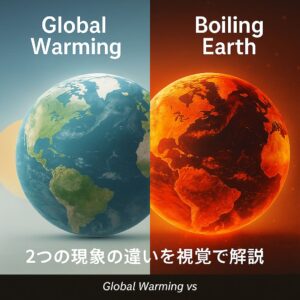
2つの現象の違いを視覚で解説
地球沸騰化はいつから始まったのか?
地球沸騰化という言葉が広まり始めたのは、2023年が大きな転機となりました。この年、世界各地で記録的な暑さが相次ぎ、「もはや温暖化ではなく“沸騰”だ」といった声が強くなったのです。
特に話題になったのが、国連事務総長による「地球温暖化の時代は終わり、地球沸騰化の時代が始まった」という発言です。この強いメッセージが多くのメディアで取り上げられたことで、一般にもこの言葉が知られるようになりました。
ただ、注意したいのは、気候の異常が突然始まったわけではないということです。実際には、長年にわたる温暖化の積み重ねが、限界を超えた結果として沸騰化という表現に至ったのです。以下の表に、関連する年と出来事を整理しました。
| 年度 |
主な出来事 |
| 2016年 |
世界平均気温が観測史上最高を記録 |
| 2021年 |
ヨーロッパ・北米で過去最大規模の熱波 |
| 2023年 |
「地球沸騰化」という言葉が国連で使用され注目 |
このように、「地球沸騰化」という現象は最近になって急に始まったように感じられますが、実際には何十年も前から続く温暖化の“結果”として現れたものだと言えるでしょう。気づくのが遅れただけで、気候は確実に変化してきていたのです。
地球沸騰化が注目されるようになった背景
近年、「地球沸騰化」という言葉が急速に広まった背景には、いくつかの大きな理由があります。
まず一つは、異常気象の増加が日常的なものになってきたことです。たとえば、夏の猛暑日がかつてよりも増え、気温40度を超える地域が日本を含めて世界中に広がっています。こうした現象が「一時的なものではなく、恒常的になってきている」と感じさせるようになりました。
次に、メディアの影響も見逃せません。地球沸騰化という言葉は、強いインパクトを持ち、読者の関心を引きつけやすいため、多くの報道で使われるようになりました。中でも国連による発言は、地球全体が“今まさに危機にある”ことを象徴するメッセージとして強く響いたのです。
さらに、SNSやネット記事の拡散によって、以前は専門的だった気候の話題が一般の人々の間にも広がりました。これにより、気候変動が「環境問題」から「日常の不安」へと変わったことも、注目される理由のひとつです。
また、以下のような社会的背景も関係しています。
| 注目が高まった要因 |
内容 |
| 異常気象の激化 |
熱波・洪水・干ばつなどが毎年のように発生 |
| 国際機関の強いメッセージ |
国連が「地球沸騰化時代」と明言 |
| SNSによる情報の拡散 |
気候関連ニュースがすぐに世界中に広まる |
| 若年層の環境意識の高まり |
学生や若者のデモ、気候行動が社会的関心を集めた |
このような要因が重なり、「地球沸騰化」は単なる言葉以上に、地球規模の異常事態を象徴するキーワードとして注目されるようになったのです。未来の問題ではなく、“今”の私たちの暮らしに直結する問題として、多くの人が関心を持ち始めています。
地球沸騰化の影響が身近に現れている例
最近、「あれ?今年も異常に暑いかも」と感じたことはありませんか?
実はそれ、地球沸騰化の影響がすでに私たちの身近に現れているサインかもしれません。
まず最もわかりやすいのは、夏の暑さが過去と比べて格段に厳しくなっているという点です。昔は30度を超えると「真夏日」と言われていましたが、今では35度を超える「猛暑日」が連日続くのも珍しくありません。東京都心や大阪市内でも、連続で熱中症警戒アラートが発令されることも増えてきました。
さらに、以下のような現象も起きています。
| 身近な影響例 |
内容 |
| 熱中症患者の増加 |
高齢者や子どもを中心に毎年数万人が搬送されている |
| 野菜や果物の価格高騰 |
気温や干ばつによる収穫量減少で、家庭の食費にも影響 |
| ゲリラ豪雨や台風の激化 |
雨量や風速が過去に比べて激しくなっている |
| 電力需要の増加と節電要請 |
冷房使用による電力逼迫が夏の常態化に |
このように、地球沸騰化はニュースの中だけの話ではなく、すでに私たちの生活の一部に入り込んでいる問題なのです。特別な知識がなくても、「去年よりも暑い」「雨の降り方が変わった」と感じたとき、それは地球規模の変化を肌で感じている証拠かもしれません。

地球沸騰化の影響を日本で実感する様子
なぜ2025年は暑すぎると言われているのか?
2025年が「史上最も暑くなる」と言われているのには、いくつかの具体的な理由があります。
単に暑くなるというだけでなく、これまでの異常気象を超える可能性が高い年として、科学者たちも警鐘を鳴らしているのです。
まず、2024年から2025年にかけてエルニーニョ現象の影響が強くなる予測があります。これは赤道付近の太平洋の海面温度が上昇し、世界中の気候に大きな影響を及ぼす自然現象です。このエルニーニョが発生すると、アジアやヨーロッパでは猛暑や干ばつが起こりやすくなります。
加えて、地球温暖化が進行した状態でエルニーニョが重なると、気温上昇のダブルパンチになるとされています。
また、2023年・2024年と記録的な暑さが続いたことで、地表や海水の温度がすでに高い状態にあります。その影響が翌年にも引き継がれるため、2025年にはさらに高温になる可能性が高まっているのです。
| 2025年が暑くなるとされる要因 |
解説 |
| エルニーニョ現象の発生 |
世界的な気候バランスの崩れを引き起こす可能性あり |
| 地球温暖化の進行 |
年々の気温上昇が蓄積し、平年より暑くなりやすい |
| 地表と海水の温度が高止まり状態 |
熱が逃げにくくなり、長期的な高温が続くリスクが高い |
つまり、2025年は自然と人為的要因が重なり合い、「暑すぎる年」になると予想されているのです。体調管理やライフスタイルの見直しも、今から準備しておくことが大切です。

未来の夏が想像以上に過酷であることを示唆
地球沸騰化と氷河期の関係とその原因とは
「地球沸騰化」と「氷河期」。一見すると真逆の現象のように思えますが、実はこの2つには深い関係があります。
どちらも地球規模の気候変動によって引き起こされるものであり、その背景には地球の長期的な気候サイクルや人間活動による環境負荷が大きく関係しています。
この章では、現在進行中の地球沸騰化が、将来的に氷河期のような寒冷化を引き起こす可能性があるのか、また、そもそも地球沸騰化がなぜ起きているのかという「原因」について、やさしくわかりやすく解説していきます。
地球の未来を考えるためにも、両者の関係を正しく理解しておくことはとても大切です。
地球沸騰化の原因は何?自然と人為的要因
地球沸騰化を止めるにはどうすればいい?
2030年に氷河期が来るという噂は本当?
地球温暖化と氷河期のサイクルの真実
氷河期は今より何度低かったの?
地球沸騰化はもう手遅れなのか?
地球沸騰化に関するよくある質問【専門家監修Q&A】
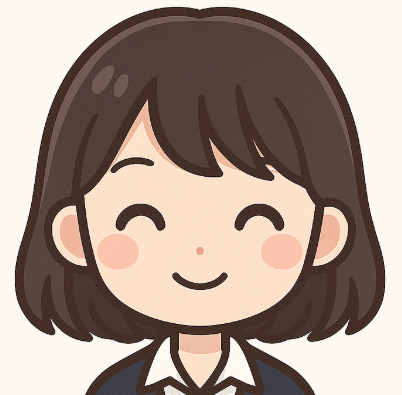
大学生みのり
「自然に気温が上がってるってこともあるのかな?それとも、やっぱり人間のせいなんでしょうか…?」
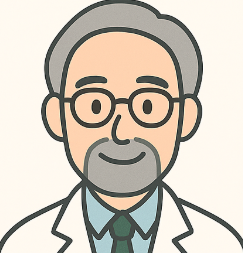
ドクター・モリ
「両方の要因が絡んでいますが、ここ数十年の急激な温暖化には、人間の活動が大きく関係しています。特に、CO₂やメタンなどの温室効果ガスの排出が大きな影響を与えています」
地球沸騰化の原因は何?自然と人為的要因
地球沸騰化の原因は、大きく分けて「自然の変化」と「人間の活動」の2つに分けられます。どちらか一方ではなく、両方の要素が絡み合って現在の急激な気温上昇を引き起こしています。
まず、自然的な要因としては、地球の自転軸の傾きや太陽活動の周期変化が挙げられます。地球は何万年というスパンで寒冷期と温暖期を繰り返しており、これが「氷河期」や「間氷期」と呼ばれる現象を生み出してきました。また、火山の噴火による大量の二酸化炭素や灰の放出も、地球の気候に影響を与えることがあります。
しかし、今の地球沸騰化を加速させている最大の要因は、人間の経済活動による温室効果ガスの増加です。
石油や石炭などの化石燃料を燃やすことで発生する二酸化炭素(CO₂)、メタン(CH₄)、一酸化二窒素(N₂O)などが大気中に蓄積し、熱を地球に閉じ込めてしまうのです。
以下の表は、主な要因とその影響をまとめたものです。
| 分類 |
主な原因 |
地球への影響 |
| 自然的要因 |
太陽活動の変化、火山噴火、海流の変動 |
一時的な気温上昇や寒冷化をもたらす |
| 人為的要因 |
化石燃料の使用、森林破壊、産業活動 |
温室効果ガスが増加し、気温上昇を加速 |
つまり、私たちの生活そのものが地球を“熱く”しているという現実があります。
これを理解した上で、どのように行動を変えていくかが、これからの地球を左右する重要なポイントです。
地球沸騰化を止めるにはどうすればいい?
地球沸騰化を止めるためには、個人・企業・国がそれぞれの立場で「できることを具体的に行動に移す」ことが必要です。
とはいえ、難しい取り組みだけではありません。私たちの日常生活でも、温暖化を抑える行動はたくさんあります。
まず、最も効果的なのは二酸化炭素の排出を減らすことです。
エネルギーの使い方を見直し、再生可能エネルギー(太陽光や風力など)を利用することで、化石燃料への依存を減らせます。家庭では、省エネ家電を選んだり、不要な照明をこまめに消したりするだけでも十分な効果があります。
次に、森林を守ることも重要な対策です。木々は大気中の二酸化炭素を吸収してくれる「地球の肺」のような存在です。植林活動の支援や、紙の無駄遣いを減らすことが、結果的に地球沸騰化の抑制につながります。
また、企業や国レベルでは、次のような取り組みが進められています。
| 対策項目 |
取り組み内容 |
| 再生可能エネルギーの推進 |
太陽光・風力・地熱エネルギーへの転換 |
| カーボンニュートラル政策 |
CO₂排出量を実質ゼロにする取り組み |
| 脱プラスチック運動 |
プラスチック廃棄物の削減や代替素材の利用 |
| 交通の電動化 |
電気自動車(EV)や公共交通の利用促進 |
このように、地球沸騰化を止めるには一人ひとりの意識が欠かせません。
「自分一人の行動では意味がない」と思うかもしれませんが、少しずつの積み重ねが大きな変化を生み出します。
今の暮らしを見直すことこそが、未来の地球を守る第一歩なのです。

日常でできる沸騰化対策をイラストで紹介
2030年に氷河期が来るという噂は本当?
「2030年に氷河期が来る」といった噂を耳にした方もいるかもしれません。この説は一部のネット記事やSNSなどで広まりましたが、現在の科学的な見解では信頼できる根拠はないとされています。
この噂の元となったのは、「太陽活動の低下」に関する一部の研究です。
太陽の黒点が減少する「マウンダー極小期」のような状態が今後起こる可能性があるという報告があり、それが小規模な寒冷化につながるかもしれないという話が一人歩きして「氷河期が来る」と解釈されたのです。
ただし、こうした自然現象が気温に影響を与えることは確かでも、人間の活動による温室効果ガスの増加がはるかに大きな影響を持っているというのが、多くの気候専門家の共通認識です。現在の地球はむしろ気温が上昇傾向にあり、「2030年に氷河期が来る」というのは現実的ではありません。
以下の表で簡単に比較してみましょう。
| 項目 |
内容 |
| 噂の根拠 |
太陽活動の一時的低下による寒冷化の可能性 |
| 専門家の見解 |
人為的な温暖化の方が影響力が大きい |
| 実際の傾向 |
気温は上昇傾向が続いている |
つまり、こうした情報を目にしたときは、不安を煽る言葉に振り回されず、信頼できる情報源をもとに判断することが大切です。

2030年の氷河期説を視覚的に表現
地球温暖化と氷河期のサイクルの真実
地球の気候は、もともと長い年月をかけて「温暖期」と「氷河期」を交互に繰り返してきたという特徴があります。この繰り返しのことを「気候サイクル」と呼びます。
このサイクルは、数万年単位でゆっくりと進むもので、地球の公転軌道や自転の傾きなど、天体の動きによって引き起こされる自然のリズムです。たとえば、地球が受ける太陽エネルギーの量が変化することで、地球全体が冷え込んだり、暖かくなったりします。
以下のように、地球の気候変動には長期的なサイクルがあります。
| サイクルの種類 |
説明 |
| ミランコビッチ・サイクル |
地球の軌道の変化による気候変動(約2万~10万年周期) |
| 太陽黒点周期 |
太陽活動の強弱による気温変動(約11年周期) |
ただ、今起きている地球温暖化はこの自然のサイクルとは異なるスピードで進んでいることが問題です。数千年かけて進むはずの変化が、わずか数十年で起きており、明らかに人間の活動による影響が強く出ています。
つまり、氷河期が将来的にまたやってくる可能性は否定できませんが、それは遠い未来の話であり、今私たちが直面しているのは「温暖化の加速」という現実なのです。
このように地球の気候は複雑で、自然のリズムと人為的な影響が重なり合って変化しています。その全体像を理解することが、未来の地球を考える第一歩になります。
氷河期は今より何度低かったの?
氷河期と聞くと、地球全体が凍りついたような極寒のイメージがありますが、実際には現代よりも平均でおよそ5〜7℃ほど気温が低かったとされています。
「たったそれだけ?」と思われるかもしれませんが、気温が数度下がるだけで地球規模では大きな変化が起こります。
たとえば、氷河期のピーク時には、現在のカナダや北ヨーロッパの多くが分厚い氷に覆われていたと言われています。
以下の表をご覧ください。
| 時代 |
平均気温(地球全体) |
特徴 |
| 現代 |
約14〜15℃ |
地域によって猛暑や寒波があるが全体的に温暖傾向 |
| 最終氷期(約2万年前) |
約7〜9℃ |
大部分が氷床で覆われ、海面も今より約120m低かった |
このように、数度の気温差が地球全体の環境や生態系を大きく左右するということがわかります。今の地球沸騰化による気温上昇も同じく、ほんの数度の違いが未来を大きく変えてしまう可能性があるのです。
地球沸騰化はもう手遅れなのか?
「もう手遅れなのでは?」という不安の声が聞かれることもありますが、現段階ではまだ間に合う可能性は残されています。ただし、すでに気候変動の影響が表れている今、対応を急がなければならない段階に入っているのは事実です。
たとえば、世界各地で記録的な熱波、干ばつ、豪雨が頻発しており、それらは人々の生活や農業、経済にも大きなダメージを与えています。これは、すでに沸騰化が「始まってしまっている」ことを示しています。
ただ、だからといってあきらめる必要はありません。CO₂排出量を減らす努力や、再生可能エネルギーの導入、森林保全などの取り組みは、地球の熱をゆるやかにする効果があるとされています。
今からでもできる対策には、次のようなものがあります。
| 対策内容 |
説明 |
| 再エネ活用 |
太陽光・風力発電を中心としたエネルギー転換 |
| 省エネ生活 |
電気やガスのムダを減らす取り組み |
| 食生活の見直し |
肉の消費を控えるなど、環境負荷を減らす食習慣 |
| 森林を守る |
木を切らずに育てる・植えることも重要なアクション |
つまり、「もう遅い」と感じて何もしないのではなく、今できることを地道に積み重ねていくことが、未来の希望をつなぐ力になります。
手遅れにしないための“最後のチャンス”に、私たちは立っているのかもしれません。

今の行動が未来を変えることを伝える象徴的イラスト
地球沸騰化に関するよくある質問【専門家監修Q&A】
Q1. 地球沸騰化とは具体的にどういう意味ですか?
A1. 地球沸騰化とは、従来の温暖化よりもさらに深刻で急激な気温上昇を指す言葉で、異常気象の頻発などが現実化している状況を表しています。2023年に国連がこの表現を使い注目されました。
Q2. 地球沸騰化の原因は何ですか?
A2. 主な原因は人間の活動による温室効果ガスの大量排出です。特にCO₂やメタンガスの増加が、気温の急上昇を引き起こしています。
Q3. 地球沸騰化と氷河期にはどんな関係がありますか?
A3. 一見真逆の現象に見えますが、どちらも地球規模の気候変動によって起こる可能性があり、長期的なサイクルの一環と考えられています。
Q4. 地球温暖化との違いは何ですか?
A4. 温暖化は比較的緩やかな気温上昇を指しますが、沸騰化は“すでに危機的状況に達している”ことを強調する警告的な言葉です。
Q5. 地球沸騰化はいつから始まったのですか?
A5. 2023年に国連が「地球沸騰化時代に突入」と表現したことがきっかけですが、気温上昇自体は何十年も前から進行しています。
Q6. 地球沸騰化で日本にはどんな影響がありますか?
A6. 猛暑日や熱中症リスクの増加、ゲリラ豪雨、農作物の高騰など、私たちの生活にも直接的な影響が現れています。
Q7. 将来、本当に氷河期が来る可能性はあるのですか?
A7. 地球には自然な気候サイクルがあり、数万年単位で氷河期が訪れる可能性はありますが、今のところ人為的な温暖化の影響が大きく、近い将来に氷河期が来るとは考えにくいです。
Q8. 地球沸騰化を止めるために個人ができることは?
A8. 省エネ生活や再生可能エネルギーの活用、食生活の見直し、森林保全など、日々の行動の見直しが大きな変化につながります。
Q9. SNSやメディアが地球沸騰化に与える影響は?
A9. SNSの拡散力により、気候危機の認知度が高まり、若年層の環境意識の向上や政策提言につながっています。
Q10. 専門家が地球沸騰化について警鐘を鳴らす理由は?
A10. 今が“取り返しがつかなくなる前の最後のチャンス”とされており、これ以上の放置が人類全体のリスクになるため、早急な行動が求められているからです。
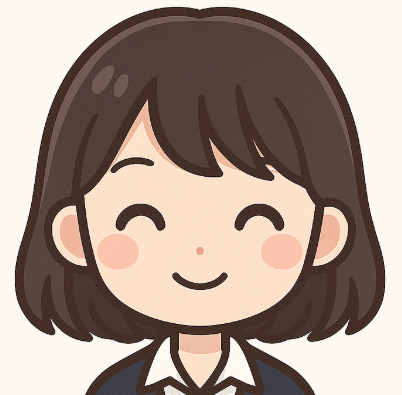
大学生みのり
「地球沸騰化って、想像以上に身近でリアルな問題なんですね…。ちょっと怖いけど、私にもできることがあるのかな?」
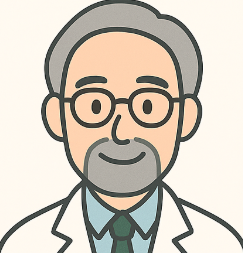
ドクター・モリ
「もちろんありますよ、みのりさん。知ることも立派な一歩です。日常の中でできる小さな行動が、未来を大きく変える力になります。希望を持って行動していきましょう」
地球沸騰化とは氷河期やその原因とどう関係するのか総まとめ
-
地球沸騰化とは、急激かつ深刻な気温上昇を指す新しい気候表現である
-
「地球温暖化」とは違い、すでに日常で影響が出ているレベルの現象である
-
地球沸騰化は2023年に国連が使用し、注目を集めた
-
現在の異常気象や猛暑の頻発がこの言葉の背景にある
-
気温上昇の要因には自然の変化と人為的要因の両方が関係している
-
とくに人間による温室効果ガスの排出が加速要因となっている
-
身近な影響としては、熱中症増加や食品価格の高騰が挙げられる
-
地球沸騰化を止めるには、CO₂削減や森林保全などの行動が必要
-
2030年に氷河期が来るという噂には科学的な裏付けがない
-
気候変動のサイクルは自然にも存在するが、現在の変化は人為的影響が強い
-
最終氷期は今より5〜7℃低かったが、それだけで大規模な地球環境の変化が起きた
-
氷河期と沸騰化はどちらも地球規模の気候変動として理解されるべきである
-
2025年が史上最も暑くなると予測される要因にはエルニーニョと温暖化の重なりがある
-
「手遅れ」とされる前に個人や社会の行動変化が必要な局面にある
-
詳しくは気象庁の特集「気象業務はいま2024」でも最新情報が確認できる(こちら)