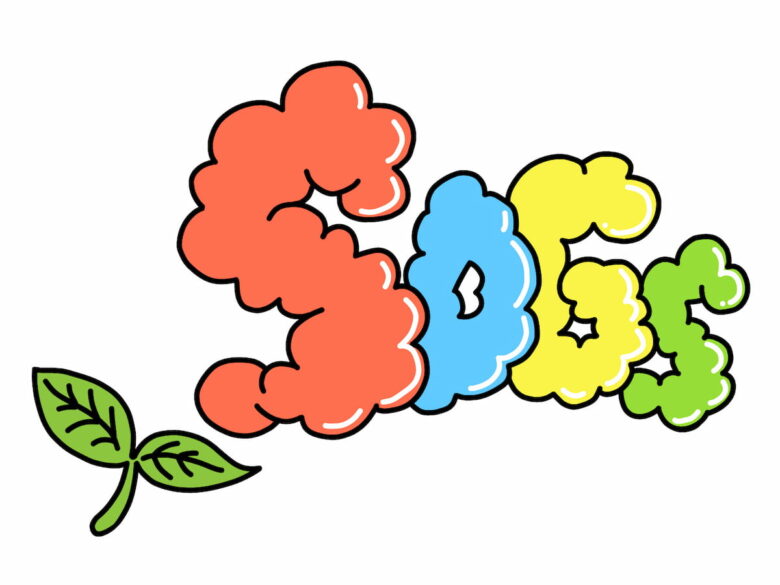環境問題に対する取り組みとして、持続可能な開発目標SDGsが世界的な常識になりつつあります。SDGsでは、地球規模の環境問題の中で世界の食料不足も取り上げられています。
大災害や突然の天変地異で文明が滅んだ世界を描いた映画や漫画でも、今まで普通の暮らしをおくっていた人が空腹に耐えきれず昆虫を食べるシーンは、食に関する究極の選択として描かれています。
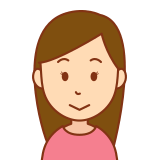
今までのシリーズを振り返ると人口増で世界中で食用の肉や魚が
不足したらスーパーに並ぶ肉は高騰するでしょうね?
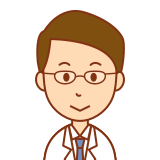
現状の畜産業なら2100年スーパーに並ぶ肉は1パックが何万円とかになる可能性はないとは言い切れないでしょうね。
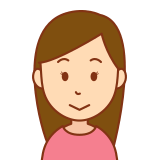
だからSDGsなんですね。ようやくわかってきました。
畜産業の穀物の代わりにセミやバッタを加工することなどがわかってきました。人間も昆虫食を好んで食べる日が来るのかな?
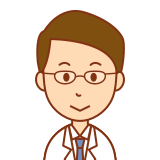
その選択も、ないとは言いきれないでしょう。
以前クジラを日本人が食べていたのが海外で批判されていたように生活や風習で昆虫を好んで食べる国もあるかもしれませんね。
昆虫食とSDGsシリーズ
世界人口は2030年には85億人を超え、2050年に97億人と100億人に迫ると、2100年ごろには110億人に達するといわれています。
2021年現在で76億人の世界人口でも不足しているたんぱく質
現在の1.5倍になる人口、伸び続ける私たちの寿命。
さらに、地球温暖化で農作物を作る場所は限られ、砂漠化が進みゲリラ豪雨が起こると食料の生産は不安定になります。
日本の食料自給率
2019年の時点でも、日本の食料自給率は食肉で52%、食用の魚介類で56%、農作物の中でたんぱく質の多い豆類は僅か7%、加工用も含めた乳製品はおよそ50%。
日本国内では、人口の半分の人の分しかたんぱく質を生産できていません。
食料の輸入競争
決して豊かではなくなった日本でも、豊かにに発展した他の国に食料の輸入競争で負けてしまい、スーパーで販売される食品が余る食品ロスは過去のものになってしまうかもしれません。
1960年代を境に減り続ける食料自給率が上がる理由は、国土も限られ、働き手も減る日本では今のところ見つかりません。
食料として昆虫が必要になることは、数10年後には避けられないことでしょう。
やはり、異文化の食卓のように、3食のどこかに昆虫食が必要になるのでしょうか?
直接食べなくても活かせる資源
昆虫は増え続ける人間にとっては、欠かせないたんぱく質になるのは避けられないことです。
ですが、セミやバッタの唐揚げや炒め物をそのまま食べなくてはならないわけではありません。
海外での取り組みパキスタン
バッタの大発生で農作物に壊滅的な被害が続くパキスタンでは、政府が農薬が散布されていない地域で捕獲されたバッタを買い取り、食用のニワトリ農家に飼料として提供する取り組みが始まっています。

イナゴ・バッタの大発生
国内での研究
日本国内でも、愛媛大学の研究チームがハエを鯛の養殖の飼料に活用する試みが続いています。
2018年に発表された『イエバエを利用した革新的養殖システムの創出』(愛媛大学教授 三浦 猛)では、20年で4倍に高騰した鯛の飼料にハエの蛹を利用することで、天然資源を保全しつつ飼料用たんぱく源を確保できるとされています。
愛媛大学の研究では、家畜の糞を利用してハエの幼虫を繁殖させ、粉末の飼料にすることで、高騰した飼料の代わりになることが明らかになりました。
ハエの幼虫と聞くと、気持ちが悪く不潔なイメージがありますが、そのままでは害虫として駆除される昆虫の命を私たちが不快感を抱かずに食べられる形で利用できるメリットがあります。
海外での取り組み・中国
実際に中国では、絹糸の生産を終えたカイコの蛹を魚の飼料に加工したシルクロースと呼ばれる商品が販売されています。
海外での取り組み・アメリカ
アメリカのインセクトテクノロジーズという企業では、食用のニワトリの畜産農家から出る糞を利用して、アブの幼虫を繁殖させ加工したフェニックスワームやカルシワームと呼ばれる飼料が2010年から利用されています。
昆虫の幼虫を食べさせたニワトリは、どうしても衛生的に嫌悪感を抱かずにはいられませんが、自然の中の生き物にとっては、はるか昔から昆虫は当たり前の食料として食べられてきました。
自然界は畜産業界にも影響
自然の中で暮らす動物は、自分たちの排泄物の中で繁殖した昆虫を食料として食べています。
新しく画期的な方法というよりも、自然の中のありのままの生活を畜産業界に取り入れた事業といえるでしょう。
この仕組みの優れた点は、処理にコストもかかり環境汚染にもなる「家畜の糞を利用」して、「駆除される害虫」を繁殖させ、「自然に近い飼料」を養殖で利用できることです。
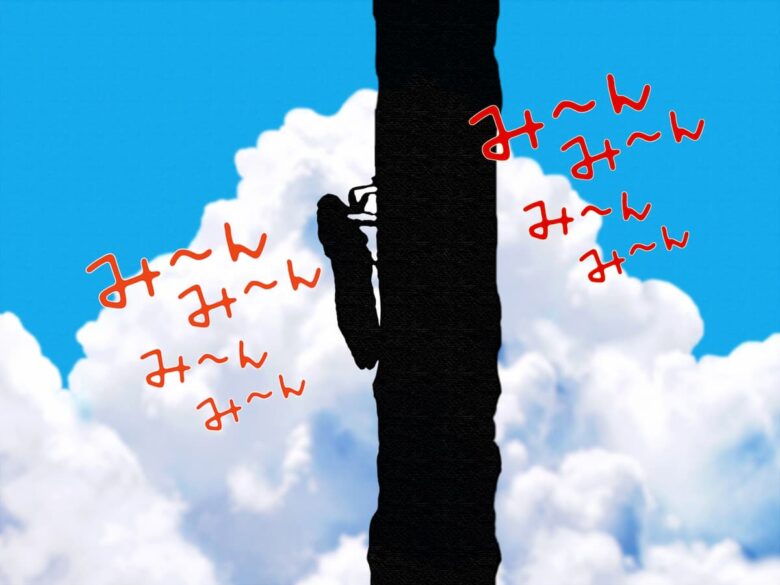
セミのイラスト
まとめ
たんぱく質を生産するという目線だけで見ると、不快感や嫌悪感がありそのままでは食べられない昆虫のたんぱく質を、元々食料としていたニワトリや魚に食べてもらうことで、人間にとっても食事の形を変えずに食べることができる点ではないでしょうか?
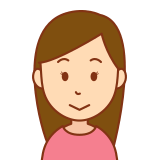
なるほど。世界中でもう既に取り組みが始まっているんですね。
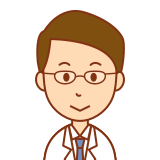
ただ、課題もあり、バッタを捕まえたり、家畜の糞でハエやアブの幼虫を繁殖させる作業が「人の手作業」に頼っている点です。
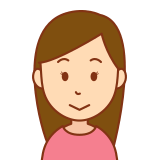
いつかは自動化され、不快感を感じたり衛生的な危険を伴わない
働き方ができることを願っています。
ではまた次回も続きますので見てね~。