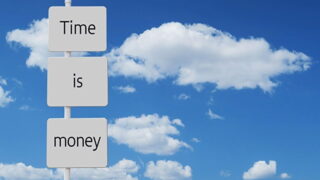天気に関することわざ四字熟語には、きちんとした理由や根拠があるものが多い中、それらには薄いものも存在します。
中には思い込みなどから出来てしまったと思われるものもあり、一見では正しそうに思えても、科学的な根拠は何もないというものも少なくありません。
今回は面白そうな天気ことわざを集めてみました。
理由や根拠が不明な天気ことわざを探究
理由や根拠が不明な天気ことわざ
ここでは、そのようなあまり理由や根拠がはっきりしていないものをいくつか挙げて、何故そのようなことわざや言葉が出来たのかという考察も加えて紹介していきます。
「三味線、太鼓の音が濁るのは雨の兆し」の科学的根拠は?

コスモス畑と雲のある青空背景
このことわざは、三味線や太鼓などの和楽器が湿気によって音色を変化させるという事実に基づいています。
湿気が多くなると、これらの楽器の皮が膨らんだり縮んだりするため、音が「濁る」ように感じることがあります。
これが雨の前触れとされたのです。
しかし、科学的な観点から見ると、これが必ずしも雨の証拠とは限らないことを理解することが重要です。
湿度は多くの要素によって影響を受け、その一部は天気とは関係ありません。
例えば、湿度は室内の温度や換気、さらには近くの水源などにも影響を受けます。
また、現代の和楽器は、より耐久性があり、湿度の変化による影響を最小限に抑えるように改良されています。
そのため、このことわざが必ずしも正確な天気予報を提供するわけではないことを覚えておくことが重要です。
しかし、先人たち(昭和初期以前、現代みたいに楽器の耐久性が低い頃)が自然の微妙な変化を観察しています。
そして、それは現代の気象学が始まった地点でもあります。
先人たちは三味線や太鼓といった和楽器は、湿気によって音が微妙に変化すると言います。
その為、それらの音がいつもより濁って聞こえる時には湿度が上がっていると判断できる為、雨が近付いているという意味のことわざです。
一見では正しいことを言っているように聞こえることわざで、三味線や太鼓ような物理的な構造によって音を奏でる仕組みの和楽器の音が湿気によって変化があるのも間違ってはいませんが、必ずしも濁って聞こえるようになるとは限りません。
更に言えば、よほど昔の楽器でない限り、多少の湿気程度で音が大きく変わるようなことはないように和楽器も進化しています。
よって、間違いとは言えないものの、そのまま捉えてしまうのは現在にはあまり適していないことわざだと言っていいでしょう。
「熊を殺すと雨が降る」
これは、昔の狩猟を専業とするマタギと呼ばれる人たちの間で囁かれていたもので、現代でも聞くことがあります。
何故そのように言われるかと言えば、山の神なる存在が、その山を熊の不浄の血で汚してしまったことに怒り、雨を降らせてその血を清めるからだと言われています。
正直なところ、神という存在が登場するだけで現実味があることわざだとはとても言えず、熊の駆除と天候にも当然何の関係もありません。
ですが、実際に熊を駆除した翌日に雨が降ると、山の神がその地を清めているのだと考えて、このことわざを口にする人たちが居るのも実情です。
その為、科学的な根拠うんぬんなどと言い出すのは無粋というものかも知れないことわざの1つだと解釈しておいてください。
「210日は嵐が来る」
この210日とは、立春から数えて210日目という意味で、9月1日頃がちょうどその日に当たります。
その頃には夏の暑さの原因となる太平洋高気圧も序々に日本列島の上空から引いていき、秋雨前線と呼ばれる前線がちょうど日本に南下してくる頃なので、天気が荒れやすくなります。
変わりやすいものの例えとして、「秋の天気と~」などということわざが別にあるように、この季節には天候が荒れることが少なくなく、間違っているとは言い切れないことわざですが、210日目とはっきりと指定してしまっていることから、根拠には薄いものだと言わざるを得ません。
ちょうど210日目に当たる9月1日やその前日に天候が大きく崩れると、やはりことわざの通りだと考える人も少なくありませんが、実際にはその程度の意味から言われているものだと考えておきましょう。
「五風十雨」(ごふうじゅうう)
5日ごとに風が吹き、10日ごとに雨が降ることの表現になる四字熟語です。そのような天気が農業にとって最も都合がいいとされており、「ここの所は五風十雨の天候で、これならいい作物が出来そうだ」などと使われています。
ですが、実際にそんな都合のいい天候が続く訳もなく、あくまで理想の天候を表現しただけのものです。
また、その通りではなくても、1週間ごとに風が吹いたり雨が降ったことで農業にとって都合がよかった時に、例えてこの「五風十雨」と使うことも多くあります。
「雨栗日柿」(あまぐりひがき)
雨が多い年には栗がよく育ち、日照りが続いた年には柿の育ちがいいという意味になる言葉です。
確かに、栗の木は水分をよく与えるほど実がよく育つと言われており、柿は多少水を与えなくても枯れてしまうことはない樹木です。
そのような点から考えると、立派な根拠があると言うこともできますが、実際に雨ばかりでは栗もまともには育たず、毎日日照り続きではいくら柿の木と言えど参ってしまいます。
科学的にデータから検証してみても、近年では平成29年に栗の生産量が前年より13%以上増えていますが、その年の年間降水量は前年より少なかったという事実があります。
よって、あくまでそのように言われているだけで、それに当てはまった時に都合よく使われることがあるという程度の言葉だというのが真相です。
天気にまつわることわざはたくさんあります。いざという時にも、天気予測の参考になるので知っておきましょう。
暑さも寒さも彼岸まで
このことわざは知っている人も多いでしょう。
夏は耐えられないような日々の暑さも、秋の彼岸のころを過ぎると途端に涼しく感じるようになります。また、冬は手足がしびれるような寒さも、春の彼岸を過ぎれば風のあたたかさを感じやすくなる、という季節の移り変わりをうまく表現していることわざです。
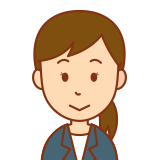
おばあちゃんに、この暑さ寒さも彼岸までだってよく聞かされたものでした。季節の変わり目を感じますね。
大根の根が長い年は寒い
大根の白い部分は根っこです。地中で育っているため、大根の生育と地中の温度とは密接な関係があります。
一般的に地温が低い地域で育った大根は細く、地温の高い地域で育った大根は太くなります。地下深くなるほど温度が一定しているため、気温が低い年は熱を求めて地下深くまで伸びてしまい、逆に暖かい年は太く短く育つ傾向にあります。
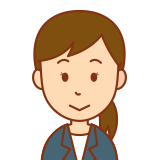
桜島大根ってなんであんなに大きいのだろうと思ってたらこういう事だったんですね。えっ私の足?あんなに大きくないですよ!失礼な~スッと細長い美脚ですよ~。
早朝暖かいときは雨
早朝は、一日のうちでもっとも気温が低くなる時間です。ところが、早朝にもかかわらず暖かいときは低気圧が近づいているというサイン。雨が降る可能性が高くなります。
四季折々の天候を表現する日本のことわざと四字熟語
日本は四季がはっきりとした国であり、それぞれの季節に特徴的な天候があります。
日本のことわざや四字熟語には、この四季折々の天候を美しく、時には風刺的に表現したものが多数存在します。
次は、それらの中からいくつかを紹介し、その由来や意味について探っていきましょう。
春の天候に関することわざと四字熟語
「春眠暁を覚えず」
春は日が長くなり、暖かさも増すため、ついつい寝坊してしまうということわざです。春の爽やかな気候が、眠りを誘うことを表しています。
「春風駘蕩」(しゅんぷうたいとう)
これは「春風が心地よく吹く」という意味の四字熟語です。春風が暖かく、落ち着いて吹き、それが人々の心を穏やかで豊かな気持ちにする様子を表しています。
「花鳥風月」(かちょうふうげつ)
「花鳥風月」は「自然の美を愛でる」という意味の四字熟語で、具体的には花(春)、鳥(夏)、風(秋)、月(冬)を象徴とする自然の四季を楽しむことを意味します。春は花が特に美しく、それを愛でることの喜びを表現しています。
「春色満园」(しゅんしょくまんえん)
「春色満园」は「春の色彩が庭いっぱいに広がる」を意味する四字熟語です。春になると花々が咲き誇り、自然が色とりどりになる様子を描写しています。
夏の天候に関することわざと四字熟語
「暑さ寒さも彼岸まで」
このことわざは、暑さのピークも冷え込む寒さも、それぞれの季節の中ごろである彼岸までと言われています。つまり、夏の暑さも冬の寒さも、彼岸を過ぎると和らぐという意味です。
「夏虫疑氷」(かちゅうぎひょう)
夏の虫が冬の氷を理解できないという意味の四字熟語です。
これは、短い夏の間しか生きられない虫が、長い冬の寒さを理解できないという事から、自分の経験しか知らないという短絡的な考えを戒める意味があります。
残暑見舞
「残暑見舞」または「残暑見舞い」は夏の終わりに送られる見舞い状や挨拶状を指し、この時期の暑さを表現するためによく使用されます。
「飛んで火に入る夏の虫」
番外編ですが、これは「無知や無思慮で自分の危険を顧みず、魅力的なものに惹かれて行動してしまう様子」を表しています。
夏の虫が火の光に引き寄せられ、その結果として火に飛び込んでしまうことからこの表現が生まれました。
魅力的なものに目を奪われて、危険を顧みずに行動してしまう人々を警告するためによく使われます。
そのため、これは夏の天候というよりは、人間の行動や人間性を描写するのによく使われる表現と言えます。
秋の天候に関することわざと四字熟語
「秋の夜長」
「秋の夜長」という表現は、秋の夜が長くなることを表しており、また、それがゆっくりと過ごすのに適していることを示しています。
「秋高気爽」(しゅうこうきそう)
「秋高気爽」は、「秋の空が高く、気分が爽やかである」という意味の四字熟語です。秋は夏の暑さが和らぎ、空が高くなり、気分が爽やかになる季節を表現しています。
冬の天候に関することわざと四字熟語
「冬来たりなば春遠からじ」
このことわざは、冬が来たらすぐに春が来る、という意味です。
つまり、どんなに寒く厳しい冬でも、その後には必ず暖かい春が訪れるという希望を表しています。
「三寒四温」
「三寒四温」は「3日寒い日が続いた後に4日温かい日が続く」ことを指します。
これは特に冬の終わりから春にかけての不安定な気候を指す表現で、日本でよく使われます。
これらのことわざや四字熟語は、先人たちが四季折々の天候を繊細に観察し、その経験を言葉にしたものです。
また、それぞれの季節の天候が日本人の生活や心情にどのように影響を与えてきたかを示す貴重な資料でもあります。
季節や天候に関することわざや四字熟語を理解することで、自然との関わりや生活の知恵、さらには日本の文化や思想を深く理解することができます。
四季折々の天候を味わいながら、これらの言葉を思い出してみてください。
まとめ
このように、特に根拠が無かったり、都合よく使っているだけのものも見られる天気に関することわざ四字熟語ですが、無理にここで紹介したような理由を挙げて、頭から否定する必要もありません。
元々ことわざや四字熟語にはそういったものが多く含まれているのは周知の通りで、それが天気に関するものにもいくつかあるというだけのことです。
調べれば調べるほど天気に関することわざや四字熟語はたくさんあると思います。
今の時代はアプリやニュースなどで天気の状態を知る事が出来ます。そんな便利ツールがなかった時代に、先人たちは知恵により天気を予想していたのです。天気ことわざや四字熟語は調べたら調べるほど面白いですね。
このような四字熟語やことわざを知っていくと、そのようなシチュエーションだという時にさっと出てくるものです。自らが使うだけでなく、人が使った際の意味が分かるようにという意味でも、面白いものを挙げてみました。